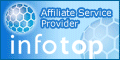生産管理講座 - 購買管理
引用サイト: http://www1.harenet.ne.jp/~noriaki/link78.html
生産管理が『設計−調達−作業』の3つの業務を持ち段階的に進む関係を持っている。
この中の調達業務についても『計画(要求)−調達(狭義)−保管(倉庫)』に分かれている。
『計画(要求)』は生産管理の一環をなしていて、材料見積もりに基づいて必要な材料の所要量と納期を決め、調達を要求することです。
『調達(狭義)』の内容には大きくは購買と外注に区分され、検収業務も含まれる。
この購買と外注は購買方針もしくは外注方針、発注と取得管理から成り立っている。
購買方針もしくは外注方針は何を、どれだけ、いつ、いくらで、どこから買うかである。
いくらで(価格と支払条件)、どこから(部品メーカー)が購買方針もしくは外注方針の問題となる。
このISO9000sの要求品質事項6番目の購買の中に、『供給者は、購買品が規定要求事項に適合することを確実にするための手順を文書に定め、維持すること』と規定されている。
『品質システム及び特定の品質保証の要求事項を含む下請負契約要求事項を満たしうる能力に基づいて、下請負契約者を評価し、選定すること』と規定されている。
つまり、下請負事業者を選定・評価する基準を設け、下請負事業者を選定し、下請負契約を交わすことになる。
工程計画(工程設計)とは、ある製品の設計図に基づき、その製品の製造方法、すなわち必要な工程(機械・治工具の種類、作業の種類、作業者数)、その順序、工程処理時間を決めることである。
その工程経路で、生産のために必要な作業(加工)について、どの程度自社内で実施するか、逆にいえばどの程度社外を利用(外注)するかという区分、つまり、内外作決定(make or buy)が重要である。
後者は生産設備を持っていることを前提にした内外作による生産調整のための決定である。
また、内外作基準は、生産機能の段階に応じて決定されると同時に、重要度によって決定する組織階層が異なる。
技術の問題は自社がある部品の設計技術・製造技術を持つか持たないかの問題である。
技術関連で内外作を決定する問題は、自社と他社のどちらが必要な特殊・重要技術を持っているかに関連する。
一般に、ある他社が優れている技術を持っていて、それを陵駕するには相当の期間と投資が必要であるとか、あるいは将来とも到底陵駕できないようであればその技術を持たない、というよりも持てないことになる。
離婚寸前まで冷え切った夫婦関係が新婚以上にラブラブに変わる秘訣!!夫婦円満に生まれ変わるセックスレス改善幸せマニュアル
調達・購買ブログ - livedoor Blog(ブログ)
引用サイト: http://blog.livedoor.jp/nomachi0306/
購買・調達支援企業の株式会社アジルアソシエイツの代表の野町が運営するブログです。
購買業務に携わるもしくは、コンサルティングをしている有志で日ごろ感じていることを自由に書き込んでもらっています。
購買・調達業務のプロフェッショナル化、キャリアの確立、近代化を目指す人達のためのブログです。どんどんご意見ください。
最近、食の安全に関してよく話題になっていますので、今日は食のサプライチェーンとサプライヤ評価について、考えたことを書きたいと思います。
皆さんご存知の北海道の食肉会社(以下、「M社」といいます)の事件で、私が意外に感じたのは、S協が同社の肉の入ったコロッケを販売していたことでした。
私の消費者として、S協から食材を買っていますが、多少高くても買っているのは、「S協であれば、変な材料を使った食材は販売しないだろう。」と言う単純な思いこみからでした。(人間の情報収集能力には限界がありますから、一般消費者が、S協というブランドを信用して購入するのは、当然のことと考えています。)
一方で、バイヤーの視点からは、S協の調達部門におけるサプライヤ評価制度やサプライヤ認定制度は、どのような仕組みなのかは興味あるところです。
M社の事件における商流は、”M社→サプライヤ(食品加工会社)→問屋→S協”ですから、S協の調達部門は、サプライヤ(問屋)のサプライヤ(食品加工会社)について、原料調達方法を管理していたか、または、その先のM社の実態を管理していたか否か問われると考えられます。
S協は、過去3年間に遡ってM社の製品を使用して製造・販売したコロッケの代金を消費者に返金すると発表しました。その損害額は数十億円に達すると言われています。しかし、調達部門が、事前に充分なサプライヤ評価をしていれば、この損害発生とS協ブランドの失墜は未然に防げたのではないかと思っています。
バイヤーの直面する課題として、どのレベル(孫受け、ひ孫受けまたはTier2、Tier3など)までサプライヤを管理すべきかがよく話題となります。
中国産玩具の有害物質問題についても同様のことが言えますが、サプライチェーンが長くかつ複雑化している現在、リスクマネジメント上の重要アイテムについては、源流まで遡って管理することが必要になってきていると考えています。
 アフィリエイトに必要な情報は何でしょうか?
アフィリエイトに必要な情報は何でしょうか?