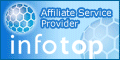企業はなぜ,在庫を持つのか:ITpro
引用サイト: http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060718/243534/
今日は,筆者の顧問先企業の一つ,切削工具の金型メーカーであるC社を訪問しました。この中堅企業のコンサルティングを引き受けたキッカケは「どのようにしたら材料や製品などの在庫と,ERPシステムのデータとを一致させることができるのか」にありました。
一致しないことがあるのか,と驚いてはいけません。これは棚卸資産の評価に,ある方法を採用していると,問題の本質が見えなくなることに端を発しています。システムを導入したのはいいが,製造現場への指導や会計処理のアドバイスが放置されることによって,問題の傷口はさらに広がります。
ERP導入を手がけたシステム・インテグレータの担当者はホワイトカラーの典型ですから,機械油や塩酸のニオイが漂う製造現場に足を踏み入れ,自らの手を汚すわけがない。そして,ユーザー企業の官僚組織と化した本社部門では,「ERP前線,異状なし」と自らの失策を糊塗(こと)した報告書が作成され,経営上層部に回付されます。
金型メーカーのC社では,社長から若手社員までが大部屋に机を並べ,風通しの良さが抜群です。これが中堅・中小企業のいいところ。まぁ,怒鳴り声が直接聞こえてしまうのが,玉に瑕(キズ)ですが。
さて,そのC社で費消される材料は超硬合金といわれるもので,グラム単位で取引されるほど高価なものです。いまでこそC社は日次で実地棚卸ができるほど,整然とした在庫管理が実現できるようになりました。しかし,筆者が最初に訪問したときは『消化仕入れ』と『自社購入』の区別がついておらず,「なんだぁ?! この渾然一体とした在庫の山は」と呆れ返り,計量器を抱えて倉庫内を走り回ることから始めました。誤って,爪を剥がしたこともありました。
ただし,今回はC社に伝授した在庫管理ノウハウや修正仕訳の紹介ではありません。企業はなぜ,在庫を持つのか,の話です。
「タカダ先生ったら,何を当たり前のことを。材料を切らしたら生産工程がストップしてしまうし,一定数量の製品在庫を確保しておかなければ販売機会を逃してしまうじゃないですか。そのために,在庫を持つんですよ」
「それもまた,いわずもがな,の問いかけですね。元帳をみれば一目瞭然です」
確かに元帳残高を見れば,棚卸資産の在高(ありだか)がわかります。しかし,それは貸借対照表上のものでしょう。コスト管理の観点からすれば,貸借対照表上のストック残高を,損益というフローの金額で見ることができるか,ということが重要です。
ほったかしで継続的に収入を稼ぎ続ける、システマチックなアフィリ手法・・・。【システムアフィリエイト】
生産管理講座 - 在庫管理
引用サイト: http://www1.harenet.ne.jp/~noriaki/link75-3.html
多くの工場では、ライン作業から分離して、工場内物流を担当する人がいる。
ライン作業者の付随作業を分離することによって、ライン作業者の効率を上げる目的で分離している。
工場内物流で重要なのは、『ルート配送』と『ダイヤグラム配送』である。
『ルート配送』はどの企業でも行なわれているが、『ダイヤグラム配送』は難しい。
特に、まとめて運ぶという考え方から抜け出せず、成り行き管理に陥りやすい。
『必要なものを、必要な時に、必要なだけ』運ぶ、若しくは部品の流れを切れ目なく行なうトヨタ生産方式の実践が必要である。
一般的な自動車工場では、工場の横一面が部品会社からの部品受入れ場になっている。
生産ラインは1台ずつ流れているので、それに合わせて部品を運ぶ必要がある。
1部品で量が多い部品は、その時間帯の中で2分割、3分割して運べは良い。
生産変動(残業の追加、時産の変動)によって、運ぶ部品量が増えたり、減ったりする。
JRのダイヤグラムには、カゲスジというものがあり、臨時列車を走らせるのに使用している。
また、部品をラインに配送した時、基準在庫より下回っているかどうかを見ることによって、在庫管理もできる。
思わぬ在庫の減少は、思わぬ部品組付け不良を出したか、カンバンが紛失している等がわかる。
どのような機種の生産が行われるかを熟知していなければ、適切に部品は運べない。
その時間を有効に使用する面からも、ライン生産の組織と一体的に運営されるべきである。
循環棚卸は3日に1回とか、1週間に1回とかで棚卸のサイクルを決めて、順次棚卸をしていくやり方である。
一般的な資材発注はABC管理とも呼ばれている方法が取られることが多い。
2:8の法則とも呼ばれているように、金額の大きな順に部品を並べ、金額の大きいほうから20%の部品数の取引額が80%の金額を占めるというものである。
例えば、金額の高い順に10%、30%、60%をA部品、B部品、C部品とする。
A部品には定期発注方式を使用し、期間内の部品所要量を正確に把握して発注する方法である。計画変更に対しては所要量計算の回数を増やして細かに対応することが多い。
また、在庫管理も厳密に行う。金額が高い部品の他に、大きさが大きくて置き場を多くとる部品、ラインストップしてしまう部品等がある。
 アフィリエイトに必要な情報は何でしょうか?
アフィリエイトに必要な情報は何でしょうか?